
近年、AI技術の進化によって、画像生成や音声認識など、さまざまな分野でAIが活躍しています。
例えばSiriやAlexaといった音声アシスタント機能、AIテクノロジーを搭載したエアコンや冷蔵庫などのスマート家電、その他にも私たちの生活にはすでに多くのAIが溶け込んでいます。
そして今、注目されているのが「動画生成AI」です。これは、テキストや画像などから自動的に動画を作り出すAI技術のことで、映像制作の常識を大きく変えようとしています。
今回のコラムでは、動画生成AIとは何か、どんなことができるのか、そしてSNSへ投稿する際の注意点まで、わかりやすく解説していきます。
「動画生成AIって聞いたことはあるけど、どうやって使うの?」「AIが作った動画って投稿していいの?」という疑問をお持ちの皆さんにも役立つ内容となっています。
ぜひ最後までご覧ください。
目次
動画生成AIとは?

動画生成AIとは、AI(人工知能)が自動で動画を作成する技術のことです。
テキストを入力するとそれに合わせた映像を生成してくれるものや、数枚の画像から動画を作り出してしてくれるタイプもあります。OpenAIの「Sora」や、Googleの「VideoPoet」などが代表的な動画生成AIとして知られています。
これまで動画を作成するには、動画を撮影した後、映像編集ソフトを使って手作業で動画を作成するのが一般的でした。
しかし2023年、動画生成AIの登場により、専門知識がなくても誰でも簡単に動画を作ることが可能になりました。
手間もコストも抑え、尚且つ高品質な動画を簡単に作成する時代を迎えました。
動画生成AIでできること
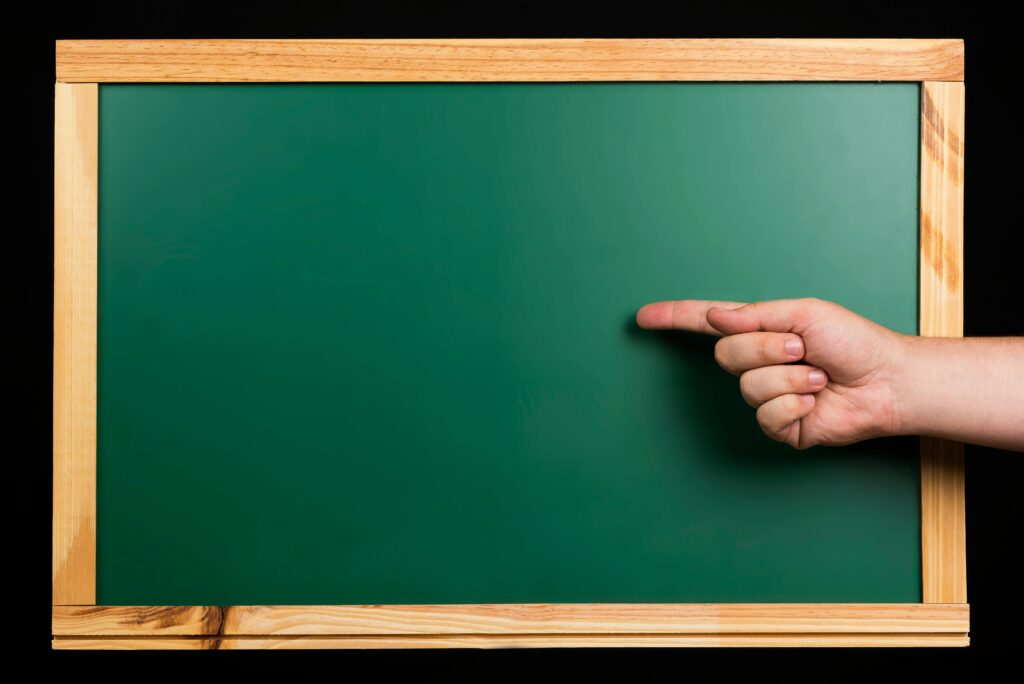
動画生成AIでできることは日々進化しています。現在の主な機能としては、以下のようなものが挙げられます。
・テキストから動画を生成
・静止画からスライドショー風の動画を作成
・アニメーション効果をつけた短編動画の生成
・既存の映像にAIで編集やエフェクトを加える
・リップシンク(口パク)付きのアバター動画の作成 など
これにより、企業のプロモーション動画、YouTubeやTikTokなどのSNS用コンテンツ、教育資料など、幅広いジャンルで動画生成AIが活用されています。
動画生成AIを使うメリット

動画生成AIの最大のメリットは、なんと言っても「誰でも手軽に動画を作れること」です。
これまでは撮影や編集に多くの時間やスキルが必要でしたが、AIを使えば、テキストを入力するだけで数分後には動画が完成することもあります。
アイデアをすぐ形にできるスピード感は、ビジネスでも個人でも大きな魅力です。
また、専門知識がなくてもまるでプロが作成したような映像を作ることも可能です。コストを抑えつつ、表現の幅をスルスルと広げられるのが動画生成AIの強みです。
最近では、リアルな人物や風景を再現できるほど精度の高い動画生成AIも登場しており、実写と見分けがつかないレベルの映像も増えてきました。
日々進化していくAI技術、それを使う私たちが本当の意味で使いこなしていけるよう、考えなければいけないことや注意すべきこともまた新たに生まれています。
AIで作った動画、SNS投稿してもOK?

動画生成AIで作った動画をSNSに投稿する際には、いくつか注意点があります。
まず前提として、動画生成AIサービスは基本的に作成した動画を個人で利用することを想定していて、商用利用や公開には制限がある場合があります。
特に注意すべき点は以下の通りです。
1.著作権やライセンスの確認
生成された動画の著作権が誰にあるのか、使用許諾がどうなっているのかを確認しましょう。
著作権法では、創作物の著作権は人間にのみ付与されます。そのためAIが生成した動画が著作権を侵害した場合、その責任はAIを使って動画を作成した人にあります。
自分の身を守るためにも、元の画像や動画に著作権があるかどうか、また、素材の出どころや利用条件をしっかり確認することが必要です。
2.人物や企業ロゴなどの使用制限
実在の人物やブランドロゴがAIにより生成された場合、それらの使用が肖像権や商標権の侵害になる可能性があります。
SNSに投稿する前に、実在する人物やロゴではないか確認する必要があります。
3.サービスの利用規約
動画生成サービスによっては、商用利用OKなもの、商用利用やSNS投稿をNGとしているものもあります。
利用規約の多くは文字が細かく、項目も多いため読むのが大変かもしれません。しかしトラブルを避けるためにも利用前に必ず規約を確認しましょう。
つまり「動画生成AIを自分が使って作ったのだから自由に使っていい」のではなく、むしろ「動画生成AIを自分が使って作ったのだから責任は自分にある」という意識を持たなければなりません。使用目的や公開範囲によっては注意が必要であり、特にSNS投稿では慎重すぎるくらいがちょうど良いでしょう。
動画生成AIの使い道と注意点

動画生成AIは、アイデア次第でさまざまな場面に活用できます。
1.動画生成AIの活用方法
まず、YouTubeやTikTokの動画制作、商品紹介や広告用の動画として印象的な作品を生成できます。広告として作成する際は、その商品の魅力がより伝わるような情報を入力すると良いでしょう。
そして、SNSでの情報発信としても効果的です。最初の数秒でバズるかどうかが決まると言われるSNSの世界。使い方によっては、ひと目で視聴者の心を掴むようなインパクトを与えることも可能です。
また、ブログやプレゼン資料の補足動画など、クリエイティブな表現が求められる場面では大きな力を発揮します。
ただし、注意点も忘れてはいけません。
2.動画生成AIを利用する際の注意点
まず注意すべきなのは、フェイク動画や誤情報の拡散リスクです。実写と見間違えるほどリアルな映像が生成できるため、悪用されると深刻なトラブルを招く可能性があります。
必要に応じて「動画生成AIを使用しています」などの注意書きを入れることも検討した方が良いでしょう。
そして、著作権や倫理的な配慮が必要です。誰かのアイデアや作品を模倣していないか、元となる画像が誰かの作品ではないか、社会的に不適切な内容になっていないかなどの確認が必要です。個人で楽しむ分には自由ですが、世間に向けて発表するとそこには責任が伴うことを忘れてはいけません。
また、AIのバイアス問題も考える必要があります。AIのバイアスとは、元となるデータや情報が歪められ、不公平または差別的な結果に繋がることを指します。
動画生成AIは、学習データに偏りがあると、意図しないステレオタイプや差別的な表現を含むことがあります。
動画生成AIは便利で可能性のあるツールですが、責任ある使い方を心がけることが大切です。
AIマネタイズについてはこちらのサイトも参考にしてみてください。
「Union AI」は、AIマネタイズやAIの活用方法を学習できるWebサイトです。
また、AIマネタイズに特化したスクールを開講しています。
いまなら無料プレゼントも受け取れるので、ぜひサイトをご覧ください。
まとめ
今回のコラムでは、目覚ましい進化を遂げている動画生成AIについて解説しました。
動画生成AIは、映像制作のハードルを大きく下げ、誰でも簡単に魅力的な動画を作れる時代を切り開いています。とはいえ、その背景には高度な技術があり、使い方によってはトラブルに繋がる可能性もあります。
今後さらに進化が予想される動画生成AIですが、クリエイターとして、また視聴者としても、その技術を正しく理解し上手に活用していくことが求められるでしょう。
動画生成AIの可能性を最大限に活かすためにも、ルールとマナーを守って安全に楽しんでいきたいですね。
最後までご覧くださりありがとうございました。





